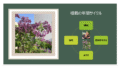高齢になると、睡眠の質と量に顕著な変化が現れ、さまざまな形の睡眠障害が発生しやすくなります。高齢者の睡眠障害は、加齢に伴う自然な生理的変化、長年の生活習慣、そして慢性疾患による身体的不調が複雑に関連して引き起こされます。
特徴的な症状として、寝つきの悪さ、夜中に何度も目覚める中途覚醒、予定より早く目覚めてしまう早朝覚醒などが見られ、これらは若年層とは明らかに異なるパターンを示しています。
これらの睡眠の変化には、体内時計の調整機能や自律神経系の変化といった生理的要因が関係します。さらに、日常活動量の変化、食事時間の乱れ、基礎疾患の存在、服用中の薬剤の影響、そして退職後の生活環境の変化やストレスなど、多くの要因が絡み合っています。
本記事では、シニア世代で増加している睡眠障害について、その特徴的な症状、発生の仕組み、そして睡眠専門医や科学的根拠に基づく効果的な対策方法を解説します。
睡眠障害の特徴
シニア世代では、加齢による身体機能や生活習慣の変化に伴い、睡眠障害が発生しやすくなります。特に体内時計の調整機能の低下、自律神経系の変化、そして日常生活のリズムの乱れが主な要因となります。これらの要因が互いに影響し合い、睡眠の質と量に大きく関わることが分かっています。以下では、主な原因について詳しく見ていきます。
睡眠の質の低下
- 加齢に伴い、深いノンレム睡眠(特に徐波睡眠)が減少し、浅いレム睡眠が増加します。その結果、わずかな物音や尿意といった軽い刺激でも目が覚めやすくなり、日中の疲労や集中力低下につながることがあります。
- 夜中に何度も目が覚める中途覚醒や、朝早く目が覚めてしまう早朝覚醒も頻繁に見られます。これらの症状は年齢とともに増加し、特に70歳以上のシニア世代に顕著に現れることが報告されています。

私の場合、自律神経が乱れやすい傾向があり、特にストレスなどで交感神経が優位になると寝つきが悪くなることがありますね。
体内時計の変化(概日リズムの前進)
高齢者は体内時計が早く進む傾向があり、夕方から強い眠気を感じ、早朝に自然と目が覚める「睡眠相前進症候群」が起こりやすくなります。この変化は、体内時計を制御するホルモンバランスの変化と密接な関係があることが分かっています。
夜間頻尿や病気の影響
- 前立腺肥大、心不全、糖尿病などの疾患による夜間頻尿により、睡眠が頻繁に中断されることがあります。この睡眠の分断により深い睡眠が得られにくくなり、睡眠の質が著しく低下します。
- うつ病、軽度認知症、パーキンソン病などの神経疾患も睡眠障害の重要な原因となります。これらの疾患は睡眠・覚醒リズムを乱し、睡眠の質そのものにも大きな影響を与えることが分かっています。
薬の副作用
降圧薬、抗うつ薬、ステロイドなどにより、不眠や中途覚醒が引き起こされることがあります。特に複数の薬を服用している場合、それらの相互作用で睡眠への影響が強まる可能性があるため注意が必要です。
日中の活動量の減少
定年退職後や身体機能の低下により日中の活動量が減ると、夜間の睡眠の質が低下します。適度な運動や社会活動が不足すると、自然な眠気を感じにくくなり、健康的な睡眠サイクルの維持が困難になります。
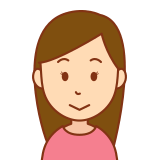
私の場合、退職後は仕事のストレスから解放され、好きなガーデニングや旅行を自由に楽しめるようになったおかげで、以前より質の良い睡眠が取れるようになりましたね。
睡眠障害の対策
高齢者の睡眠障害への対策は、原因を特定し、それぞれの要因に合わせたアプローチが重要です。
生活習慣の改善
- 規則正しい睡眠・覚醒リズム: 毎日一定の時間に就寝・起床することを心がけましょう。
- 日中の活動: 適度な運動や活動を取り入れ、自然な眠気を促しましょう。ただし、就寝3~4時間前の激しい運動は避けてください。
- カフェイン・アルコールの制限: 就寝前のカフェインやアルコールは睡眠を妨げます。特にアルコールは、一時的に寝つきが良くなっても、夜中の目覚めの原因となります。
- 禁煙: ニコチンには覚醒作用があるため、禁煙を心がけましょう。
- 昼寝の調整: 昼寝は15時までに15~20分程度とし、長時間の昼寝は夜の睡眠に支障をきたすため控えましょう。
- 就寝前のリラックス: ぬるめの入浴、軽い読書、落ち着く音楽など、自分に合ったリラックス方法を実践しましょう。
- 眠くなってから就寝: 眠気を感じないうちに布団に入ると、かえって寝つきが悪化します。眠気を感じてから床につきましょう。

環境の整備
- 寝室の調整: 快適な温度や湿度を保ったうえで、遮光カーテンで部屋を暗くし、静かな環境を作るなど、快適な睡眠環境を整えましょう。
- 寝具の見直し: 枕や布団など自分の体に合った寝具を選びましょう。
その他の対策
- 光療法: 概日リズム睡眠障害の場合、朝に光を浴びることで体内時計を調整する光療法が有効な場合があります。
- 運動療法: 軽いウォーキングなどの有酸素運動は、睡眠の質を改善する効果が期待できます。
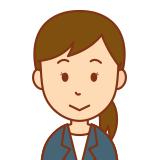
他にもYouTubeなどでツボ押しやマッサージ療法の紹介動画が多く公開されていますね。効果には個人差がありますが、参考にしてみる価値はあるでしょう。
医療機関への相談
生活習慣の改善だけでは睡眠障害が改善しない場合は、医療機関を受診しましょう。
- 原因の特定: 医師に症状や生活習慣を詳しく伝え、睡眠障害の原因を明らかにしてもらいましょう。
- 適切な治療: 睡眠薬による薬物療法や認知行動療法などの非薬物療法について、医師と相談しましょう。高齢者は薬の副作用が出やすいため、医師の指示を必ず守って服用することが重要です。
- 基礎疾患の治療: 高血圧、糖尿病、うつ病、軽度認知症など、睡眠障害の原因となる可能性がある基礎疾患がある場合は、しっかりと治療を行いましょう。

ストレスなどによる不眠時には、医師から処方されたオレキシン受容体拮抗薬ベルソムラを服用しています。副作用が少なく、依存性もほとんどないため、安心して使用していますね。
おわりに
高齢者の睡眠障害は、QOL(生活の質)の著しい低下を引き起こすだけでなく、身体機能や免疫力の低下、認知機能の衰えなど、様々な健康上の問題につながる可能性があります。そのため、症状が現れた際には自己判断による対処を避け、主治医に相談し、科学的根拠に基づいた適切な対策を講じることが重要です。
高齢者の睡眠障害には、加齢による自然な生理的変化に加え、日々の生活習慣や既存の疾患が大きく影響します。さらに、心理的なストレスや社会的な要因も睡眠の質を左右する重要な要素です。これらの問題に対処するには、規則正しい生活リズムの確立、個人に適した運動の実施、快適な睡眠環境の整備など、包括的なアプローチが欠かせません。
健康長寿の実現には、バランスの取れた食事や適切な運動とともに、質の高い睡眠の確保が不可欠です。特に高齢期では、睡眠の質が日中の活動や心身の健康状態に大きく影響します。睡眠障害に陥ると、不安や焦りが生じ、それがさらに症状を悪化させる悪循環を招きやすいため、早期の対応が重要です。
生活習慣の改善や自己管理だけでは症状が改善されない場合は、迷わず医療機関を受診し、専門医による適切な診断と個々の状況に応じた治療を受けましょう。睡眠障害の改善こそが、豊かで活力ある高齢期の生活を送るための重要な鍵となります。
《 参考情報 》